 料理
料理 談合坂サービスエリア上りのやまめ・いわなの炭火焼き「甲斐御正」
緊急事態宣言の中、釣りにも行けない、STAY HOMEということで、ブログ記事を書こうか、ということで、釣り人視点で、お気に入りのお店を紹介していこうと思います。私にとって、魚と言えば、釣りキチ三平で見た、川魚の串焼きが、衝撃でした。その魚...
 料理
料理 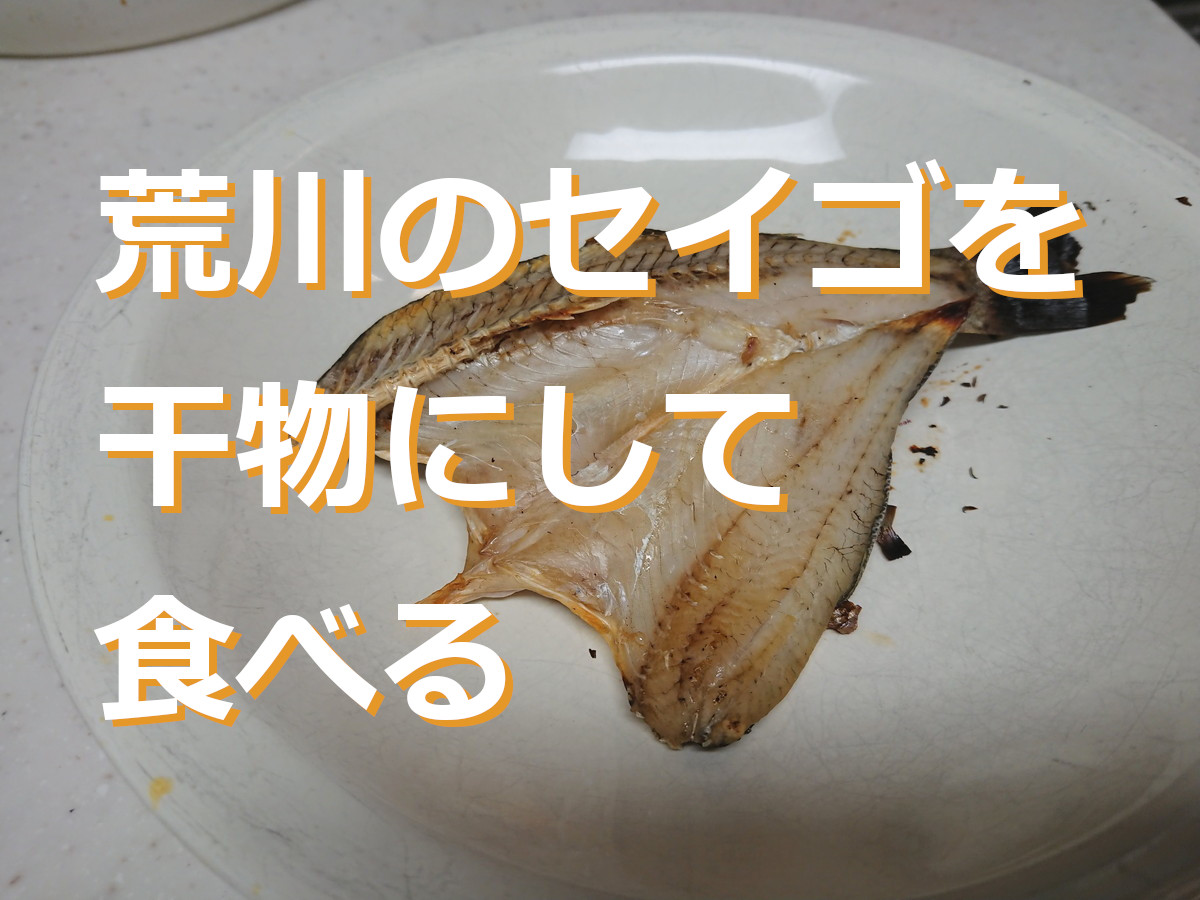 シーバス
シーバス 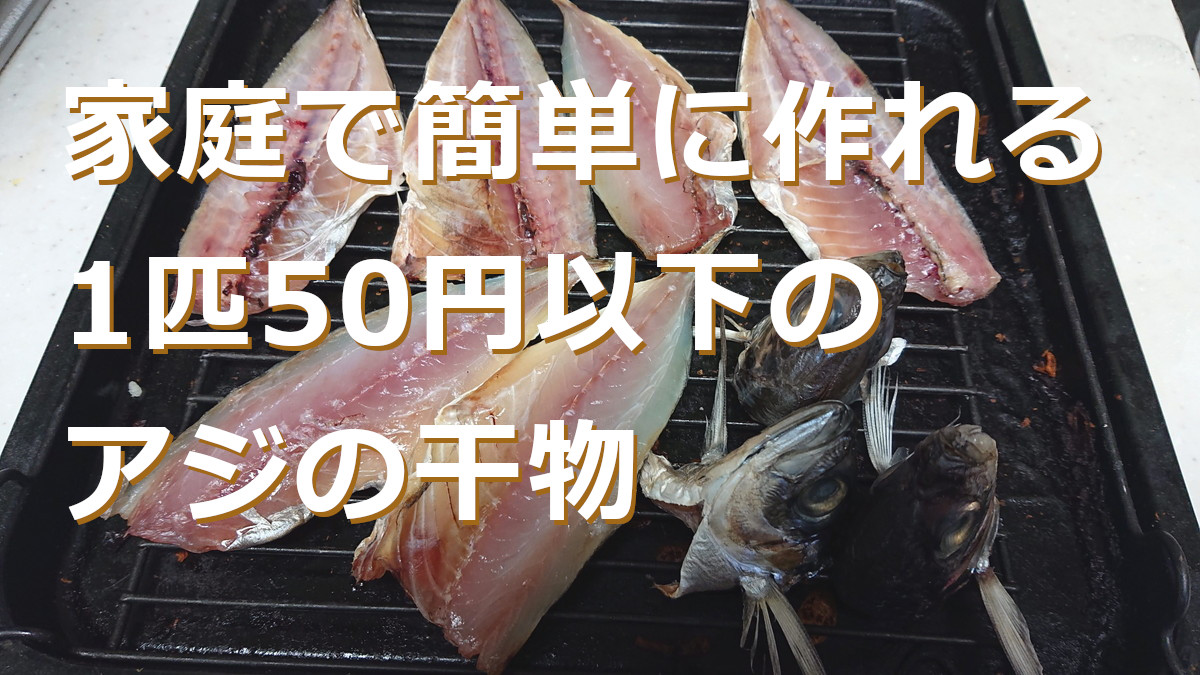 アジ
アジ  ハゼ
ハゼ  姫鯛
姫鯛  マグロ
マグロ  姫鯛
姫鯛  カレイ
カレイ  カレイ
カレイ  メバル
メバル